我慢の限界は、自分でも気づけないくらい静かに訪れる。
\原作は富士屋カツヒトさんの医療漫画/
放送日時

2025年7月13日(日)
21:00スタート
TBSテレビ
予告動画はこちらからご覧いただけます
「19番目のカルテ」 公式サイトはこちらからご覧いただけます
この記事にはドラマの内容に関するネタバレが含まれています。未視聴の方はご注意ください
見どころ紹介
第2話で描かれたのは、体の弱い弟を支え続けてきた兄の物語。
弟を優先する家族のなかで、お兄ちゃんはずっと「いい子」でいようとしてきた。
でも、それは気づかないうちに、自分の“心”をどこかに置き去りにしてしまうことでもあった。
弟が亡くなった今、ぽっかり空いた喪失とともに、これまで我慢してきた感情があふれ出す。
それに気づいたのが、総合診療医・徳重先生だった。

総合診療科とは「人を診る場所」
このドラマが繰り返し伝えてくれるのは、“総合診療医は、症状ではなく“人”を診る存在だということ。
目の前にある体調の異変だけでなく、その奥にある気持ちや生活、長年にわたる我慢や孤独までも含めて向き合う。
それは、時間も根気も必要な仕事。
でも、患者自身が「洗いざらい」語ることができたとき、不思議と心の奥にしまっていた“後悔”や“怒り”が浮かび上がってくる。
そしてようやく、自分と向き合えるようになる。
すぐに治るわけじゃないけど、時間が薬になることもある。
それを信じて待ってくれる医師がいることこそが、総合診療科の大切な意味だと思いました。

ドラマ内で登場した症状と知識
【熱中症】とは?
熱中症とは、高温・多湿の環境下で体温調節がうまくいかず、体にさまざまな不調が現れる状態です。
気づかずに放っておくと、重症化し命にかかわることもあります。
熱中症の主な原因
- 気温が高い・湿度が高い
- 風通しの悪い場所での長時間の活動
- 十分な水分や塩分の補給ができていない
- 高齢者や子どもは特に要注意(体温調整機能が弱い)
熱中症の症状
症状は軽度から重度まで段階的に進行します。以下のような症状が見られたら注意が必要です。
| 程度 | 症状例 |
|---|---|
| 軽度 | めまい、立ちくらみ、大量の汗、筋肉のけいれん |
| 中等度 | 頭痛、吐き気、倦怠感、集中力の低下 |
| 重度 | 高熱(体温が40度以上)、意識障害、けいれん、筋肉が壊れて腎機能障害を起こすことも(横紋筋融解症) |
ドラマでは、高熱によって筋肉が壊れ、腎不全を引き起こす危険なケースが描かれていました。
熱中症の対処法
| 対処法 | 内容 |
|---|---|
| ① 涼しい場所へ移動 | 日陰やクーラーの効いた室内へ。車内の場合はエンジンとエアコンをつけた状態で。 |
| ② 衣服を緩めて風通しをよく | きついベルトやシャツのボタンを外し、うちわや扇風機で風を送る。 |
| ③ 水分と塩分の補給 | 冷たい水やスポーツドリンクをこまめに摂取。※意識が朦朧としていたら飲ませない。 |
| ④ 体を冷やす | 首・脇の下・太ももの付け根などを保冷剤や濡れタオルで冷やす。 |
| ⑤ 病院へ(救急要請) | 意識障害、会話が困難、嘔吐などの重度症状があればすぐに救急車を呼ぶ。 |
熱中症予防のポイント
- 高齢者や子どもには気配りを:声かけ・室温調整を忘れずに。
- 暑さに慣れていない時期は無理をしない:特に梅雨明け直後は注意。
- 外出時は帽子・日傘・涼しい服装を意識:風通しの良い素材がおすすめ。
- 水分は「喉が渇く前に」こまめに摂る:塩分補給も忘れずに。

\原作は富士屋カツヒトさんの医療漫画/
【機能性神経症状症】とは?
検査では異常が見つからないのに、神経症状が現れる病気です。
医学的に説明できる損傷や病変はないのに、以下のような症状が現れます。
主な症状
- 足に力が入らず歩けない(運動麻痺)
- 手が震える、けいれんが起こる
- 視野が狭くなる・見えにくくなる
- 声が出ない、飲み込みにくい
- 意識を失ったような状態になる など
※あくまで「”本人が演技”しているのではなく、無意識のうちに症状が出てしまう」のが特徴です。
背景にあるもの
- 精神的なストレスやトラウマ
- 長年の我慢・心的負担
- 家庭環境、対人関係の問題
症状は“心のSOS”が、体を通して表れているような状態です。
対処法・治療法
| 対処法 | 内容 |
|---|---|
| 1. 否定せず、まずは受け止めること | 「気のせい」「思い込み」などと否定されると、本人はさらに苦しみます。信じてくれる人の存在が回復の鍵になります。 |
| 2. 心療内科・精神科の受診 | 原因が脳や神経ではないと分かったら、ストレスや感情と向き合う治療が大切になります。 |
| 3. 作業療法・リハビリ | 実際の動きを少しずつ取り戻すために、無理のない訓練が行われます。成功体験が自信につながります。 |
| 4. カウンセリングや認知行動療法(CBT) | 自分の考え方のクセや心のパターンに気づくことで、少しずつ症状が改善していきます。 |
| 5. 時間の経過も治療の一つ | すぐに治るものではなく、「気づき」「対話」「時間」が何よりの薬になることもあります。 |
「異常がないのに動かない」と言われると、本人が責められやすいですが、症状は本物です。
ドラマのように、“話を聞いてくれる医師”がそばにいるだけで、症状が軽くなることもあるのです。

\原作は富士屋カツヒトさんの医療漫画/
【ヤングケアラー】とは?
ヤングケアラー(Young Carer)とは、本来大人が担うべき介護や家事、家族の世話を、18歳未満の子どもたちが日常的に行っている状態をいいます。
たとえば:
- 病気や障害を持つ親や祖父母の介助
- 幼いきょうだいの世話
- 家事全般(料理・洗濯・掃除)
- 精神的に不安定な家族のサポート
- 日本語が話せない親の代わりに通訳や手続き代行
こうした状況は、一見“親孝行”や“しっかり者”と見られがちですが、実は子どもにとって大きな負担であり、社会問題とされています。
ヤングケアラーが抱えるリスク
- 学校での集中力や成績の低下
- 友達との交流不足、孤立
- 進学・就職の選択肢が狭まる
- 心身の不調(疲労、うつ、無気力)
- 誰にも相談できず、「助けて」と言えない
子どもでありながら“大人の役割”を引き受け続けることで、自分の人生や夢を後回しにしてしまうこともあります。
社会としてできる対応策
| 対応 | 内容 |
|---|---|
| 1. 学校や地域での早期発見 | 教師や地域支援者が「何かおかしい」と気づき、声をかけることが第一歩。 |
| 2. 相談窓口の整備と周知 | ヤングケアラー支援の専門窓口(自治体・NPO等)を紹介し、「助けを求めてもいい」環境づくりが必要です。 |
| 3. 学校・医療との連携支援 | スクールソーシャルワーカー、医療機関、地域包括支援センターなどが情報共有して支援に当たる体制が重要です。 |
| 4. 家族全体への支援 | 子どもだけでなく、家庭全体が「支援される側」としてアプローチを受けることが根本的な解決につながります。 |
| 5. 偏見のない社会づくり | 「甘えている」「しっかりしてるから大丈夫」などの無理解を減らし、共感と理解で支える社会が必要です。 |
ヤングケアラーは、ただ「家族を助けたい」という思いでがんばっている子どもたちです。
けれども、その思いが限界を超えてしまう前に、「誰かが気づくこと」こそが最大の支援になります。
ドラマがこのテーマを扱ってくれたこと自体、とても大きな意味があると思います。
こうした知識をドラマの中で自然に取り上げてくれるのも、この作品の魅力。医療と社会、そして“心”のつながりを丁寧に描いています。
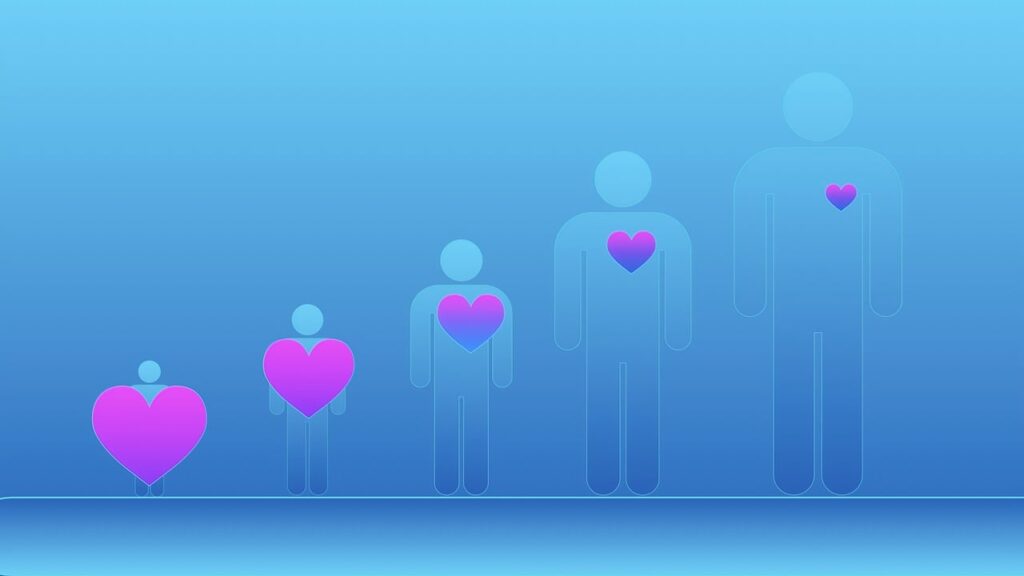
個人的な感想
「これからの話をしよう」という言葉が、とても胸に残りました。
過去は変えられないけれど、未来は選べる。
そして、未来を考えるためには、まず“自分の気持ち”を受け止めることから始まる。
総合診療科という存在は、まさにその“最初の一歩”を支える場所なんだと思いました。
診断するだけでなく、「あなたの声を聞いていますよ」と言ってくれるような存在。
これからの時代、そんな医師が増えていくことを心から願いたくなる回でした。
次週は
咽頭がんを抱えるアナウンサーの男性。徳重先生の診察が、どんな言葉と眼差しで向き合うのか――じっくり見守りたいです。

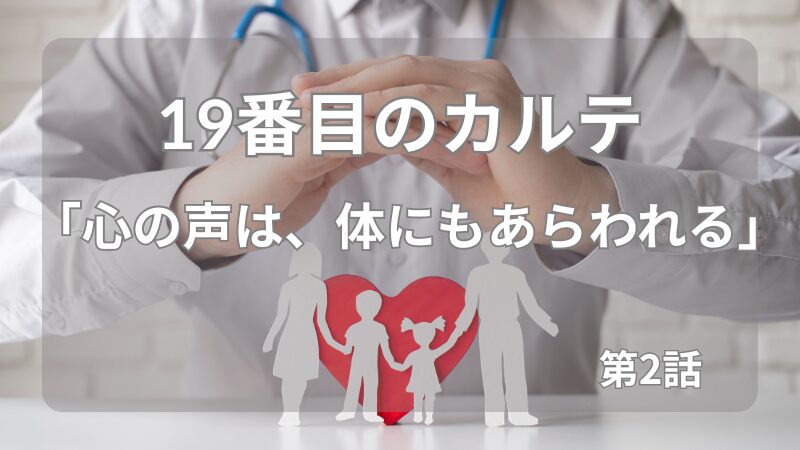


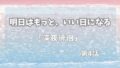
コメント