母として子どもを守りたいと願いながらも生活苦と負の連鎖に苦しみ、自分の弱さと向き合う物語。
放送日時

2025年7月7日(月)
21:00スタート
フジテレビ
予告動画はこちらからご覧いただけます
「明日はもっと、いい日になる」 公式サイトはこちらからご覧いただけます
この記事にはドラマの内容に関するネタバレが含まれています。未視聴の方はご注意ください
ネグレクトが生む負のループと向き合う現実
第7話では、安西夢乃さんの過去と現在の葛藤が描かれていました。
子どもをネグレクトしてしまい、一時保護されている状況。
子どもと再び一緒に暮らすためにプログラムを受け、学び直そうとしているのに…特有の詐欺のバイトを辞められず、逮捕寸前の危機に。
「一度ハマってしまうと抜け出せない」― その言葉が重く響きました。
生活ができない → 借金する → 返せない → また生活できない。
そんな負のループから、なかなか抜け出せない現実。

「家庭復帰支援プログラム」とは?
子どもと再び一緒に暮らすためのプログラム。
児童相談所や自治体が、一時保護・施設入所した子どもを家庭に戻す前に、親が適切に養育できるかどうかを確認・支援する仕組みです。
主な内容
① 親の生活・養育態度の改善支援
- 育児・家事の基本を学ぶ(食事・衣服・睡眠の整え方)
- 子どもとの関わり方、しつけ方を見直す
- ネグレクトや虐待があった場合、その原因(ストレス・依存・孤立)を一緒に整理する
② 心理的支援
- 親へのカウンセリング(育児不安、うつ、DV被害など)
- 子どもの心のケア(不安、愛着障害など)
③ 親子関係の再構築
- 定期的に子どもと面会し、関係を回復していく
- 親子で一緒に過ごす練習をする(週末里帰りや短期外泊)
④ 社会的な見守り
- 家庭訪問で状況をチェック
- 支援者(児童福祉司、家庭支援員)が定期的に相談に乗る
- 経済的な問題があれば生活保護や手当、就労支援に繋ぐ
プログラムのゴール
- 子どもにとって安全で安心できる家庭が整ったかどうかを確認する
- 親が「再びネグレクトや虐待を繰り返さない」ための環境づくり
- 家庭に戻しても大丈夫と判断されれば、子どもは再び暮らせるようになる
ドラマで描かれていた「プログラム」は、ただの形式ではなく、「親が子どもとどう向き合えるのかを見直す時間」だと感じます。
“もう一度やり直したい”という気持ちが本物なら、きっと子どもと暮らす未来につながる。
でも、形だけ従っているなら…その先に待つのはまた同じ悲劇かもしれません。
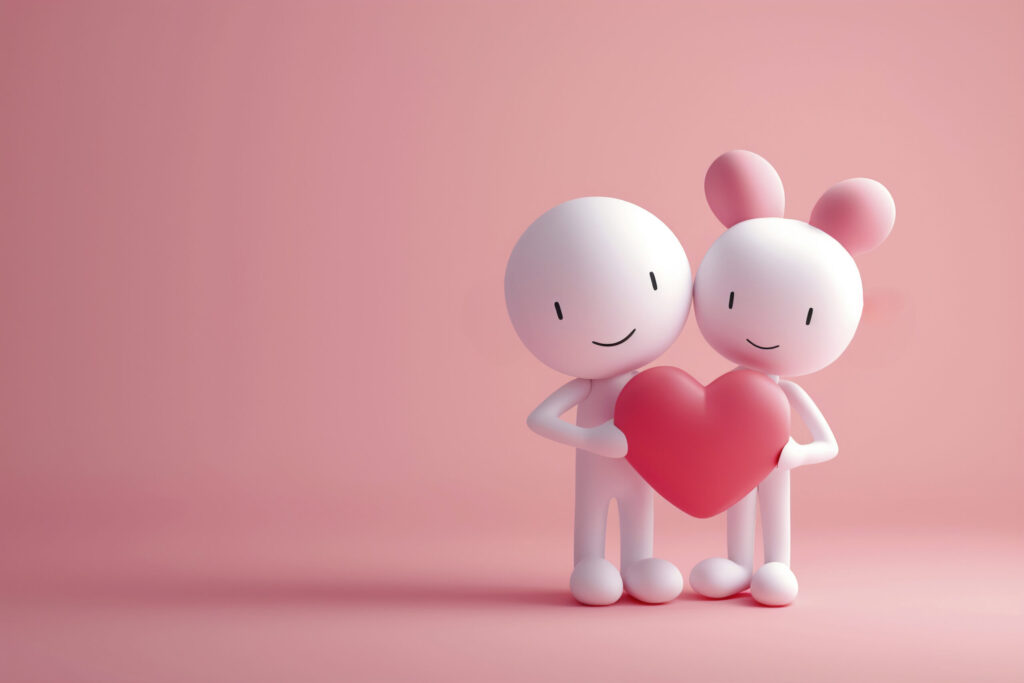
「親ってどうやんの?」普通がわからない苦しさ
夢乃さん自身も、子どもの頃にネグレクトを受けて育ちました。
「絶対に自分は母親と同じことはしない」そう思っていたのに、気づけば同じ道を歩んでしまう。
「親ってどうやんの?幸せって?家族って何?」
普通のことがわからないという言葉に、胸が痛みます。
体の傷は消えても、心の傷は消えない。虐待を受けた子どもが大人になっても抱える“見えない傷”が、まさにここにありました。
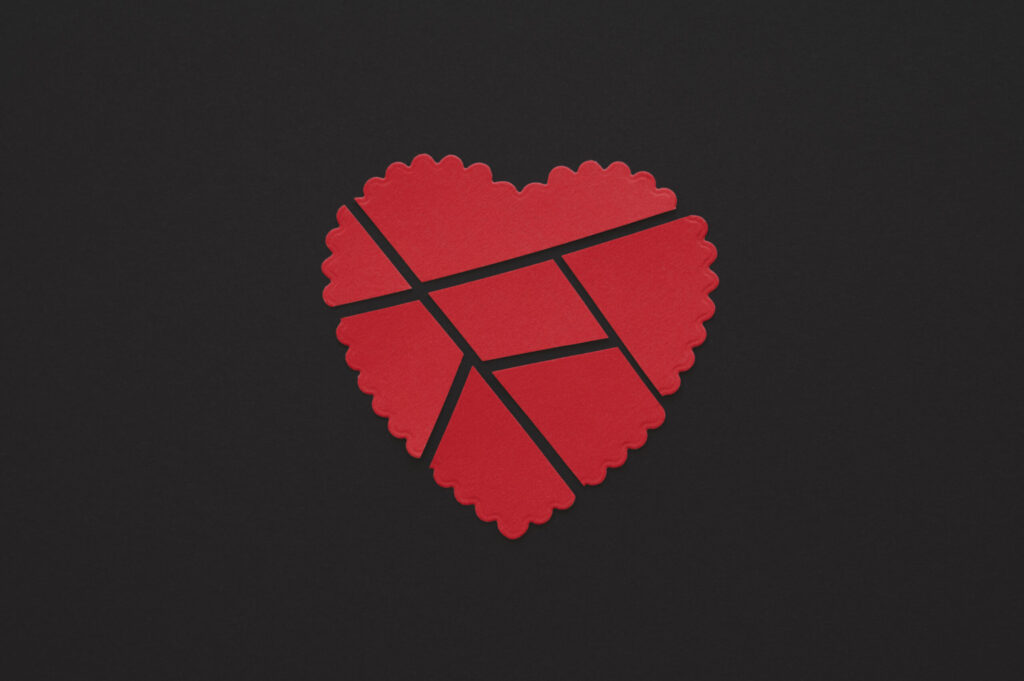
本当は優しい人だからこその苦しみ
印象的だったのは、夢乃さんが「間違ったことをしたらごめんなさい。逃げたらダメ。弱い人間になっちゃうから。」と語る場面。
彼女は本当は優しい人で、人の気持ちがわかる人。だからこそ、自分の過去を思い出すと怖くなり、「また同じことをしてしまうのでは…」と不安に押しつぶされてしまう。
親として子どもを愛しているのに、その愛し方がわからない。
その苦しさが、観ている側にも痛いほど伝わってきました。

感想まとめ
夢乃さんは「悪い母親」なんかじゃなくて、「普通の母親になりたかった人」なんだと思います。
ただ、過去の傷と貧困という現実が、その道をふさいでしまった。
子どもの気持ちに寄り添うことはできるのに、自分の弱さから抜け出せない。
その矛盾に苦しむ姿に、人間の弱さと強さの両方を見せられたような気がしました。
この物語を通じて改めて思うのは、「虐待は世代を超えて連鎖する」という現実と、それでも「誰かが寄り添えば断ち切れるかもしれない」という希望です。

次週の見どころ「里親」
次回は、カレンちゃんが里親に引き取られるお話。
「家族」とはなにかを問い続けるこのドラマで、血のつながりを越えた新しい家族の形が描かれます。
夢乃さんのエピソードとつながる部分も多く、きっと胸に残る回になるはず。

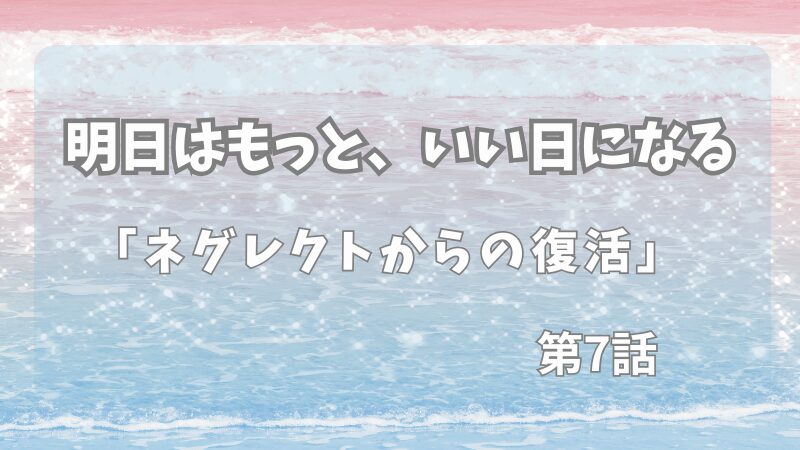
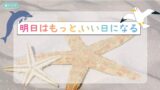


コメント