子どもが描いた絵に、心の叫びが隠されていた――。
第4話は児童心理士や保育士のまなざしを通して、
「気づいてくれる誰か」の存在がどれほど大きいかを教えてくれました。
寄り添うこと、信じること、その意味を考えたくなる回です。
放送日時

2025年7月7日(月)
21:00スタート
フジテレビ
予告動画はこちらからご覧いただけます
「明日はもっと、いい日になる」 公式サイトはこちらからご覧いただけます
この記事にはドラマの内容に関するネタバレが含まれています。未視聴の方はご注意ください
ケース①:深夜徘徊を繰り返す少女・葉月ちゃん
「誰かに愛されたかった」
その言葉が、ずっと心に残っています。
親はお金だけは与える。
でも関心も、愛情も、まなざしもない。
彼氏には利用され、親からは邪魔者扱いされる。
でも彼女には、5年間も毎週水曜日に面談を続けてくれた児童心理士・蒔田さんがいた。
「生きていれば何とかなる」
「ただ苦しくなったら、いつでも頼って。そばにいるから」
この言葉たちは、ただの支援ではなく、“希望の種”のように聞こえました。
人は、人によってしか救われない。
だからこそ、そばにいるという覚悟は、何よりも強い支えになるのだと感じさせられました。

児童心理士とは?
児童心理士とは、主にこども(0〜18歳)を対象に、その心の状態や発達、家庭環境などを専門的に支援する心理の専門職です。
児童相談所や学校、医療機関などで働き、こども自身の問題だけでなく、親や家庭の背景まで含めてアプローチします。
児童心理士ができること
- 心の悩み・不安をカウンセリングで受け止める
- 行動や感情の変化を心理検査や面接を通じて分析する
- 虐待や不登校、発達の遅れなどのケースに関わる
- 保護者や学校、福祉機関と連携しながら支援の方向性を考える
- 児童相談所では「児童福祉司」や「保育士」とチームで動く
児童心理士と臨床心理士は違うの?
実は児童心理士という資格は公的な国家資格ではありません。
多くの場合、「臨床心理士」や「公認心理師」などの資格を持った人が、児童分野で働いていることを指して「児童心理士」と呼ばれています。
つまり、「児童心理士」は役職や勤務先での呼び方であり、心理職全体の中でこどもに特化した専門家という立場です。
ドラマに見る児童心理士の役割
児童心理士は、目には見えない子どもの心の声を受け止め、
一緒に悩み、考え、希望へとつなぐ大切な存在。
「そばにいるよ」と言える大人が一人いるだけで、
子どもは少しだけ、安心して泣けるようになるのかもしれません。

南野さんの言葉のあたたかさ
もうひとつ印象に残ったのは、保育士・南野さんの一言。
「極論、美味そうに飯を食ってたら何とかなる」
これは、経験からくる本音なんだと思います。
人として当たり前のことができる環境、それこそが大事だというメッセージ。
言葉にしなくても、見ていればわかることがある。
ケース②:「向き合います」と言った母親は、本気なのか?
ネグレクトで保護された子どもたちの母親が、なんと名誉毀損で児相を訴える。
しかし、最終的には訴えを取り下げ、プログラムを受けることに同意する。
「子どもと一緒に暮らしたい」と語る姿もあったけれど…
どこか、うわべだけに見えてしまう。
HTP法(家・木・人の絵を描く検査)とは?
HTP法(House-Tree-Person Test)とは、
「家・木・人」の3つの絵を描いてもらい、その内容から心の状態や性格、家庭環境、抱えているストレスなどを読み取る心理検査です。
アメリカの心理学者バック(Buck)が1948年に開発した検査で、
子どもはもちろん、大人にも使われる**“投影法”のひとつ**として広く用いられています。
なぜ「家・木・人」を描くの?
- 家(House):家庭、安心感、帰る場所、自分の居場所
- 木(Tree):成長、エネルギー、生命力、自己像の一部
- 人(Person):対人関係、自分自身や身近な他者へのイメージ
この3つは、人が心の中で大切にしている象徴とされており、
描かれ方から、その人の深層心理や葛藤、安心・不安の感じ方が浮かび上がるとされています。
HTP法で注目されるポイント
家の絵では…
- ドアや窓がない → 閉ざされた心、誰にも入ってほしくない
- 窓が黒く塗られている → 外に見られたくない、秘密や恐怖
- 屋根が壊れている・煙突がない → 家庭の保護が不十分、家族機能の欠如
木の絵では…
- 幹が細く弱い → 自信がない、エネルギー不足
- 枝が少ない/枯れている → 希望が持てない、抑うつ状態
人の絵では…
- 顔がない・手がない → 自己表現ができない、人との関わりが怖い
- 体のパーツが欠けている → 自分を否定している、トラウマ反応
子どもの絵は「心の声」
HTP法は、ことばで気持ちを表すのが難しい子どもたちの心を“絵”というかたちで映し出す大切な手段です。
「話せない」「わからない」と思っていた気持ちが、絵にはちゃんと表れている――
それを読み取ってくれる大人の存在が、子どもにとっての“味方”になるのです。
第4話で児童心理士が見せた、子どもが描いた“ドアのない家”。
あの絵には、まさに「誰にも助けを求められない」子どもの気持ちが込められていたのだと思います。
言葉にならない痛みを、静かにすくい上げるこの検査は、
“気づき”のきっかけとして、とても大きな意味があると感じました。
感じたこと
このドラマがすごいのは、子どもの言葉にならない気持ちを、丁寧にすくい上げてくれるところ。
今回も、「生きていてほしい」「ただ、誰かに気づいてほしい」
そんな小さな叫びが、たくさん散りばめられていました。
ときに支援者の無力さも映し出されるけれど、
それでも「そばにいる」と言い続けてくれる人がいる限り、
きっと子どもたちはどこかで希望を持てる。
そう思わせてくれる、静かで力強い回でした。

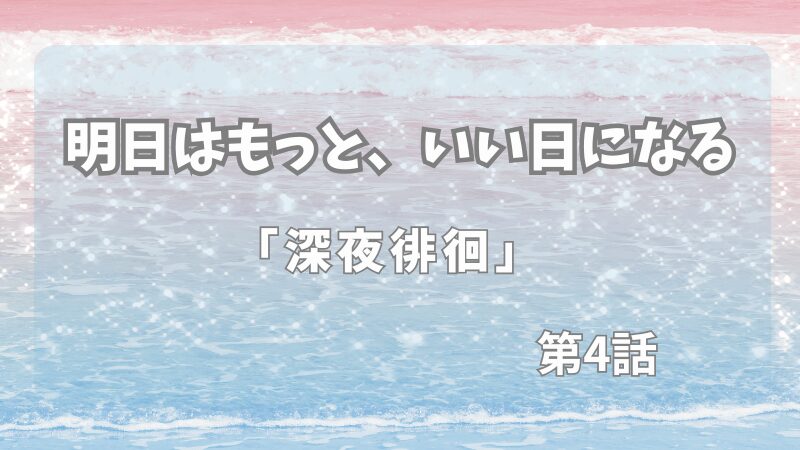
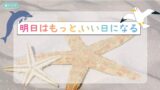


コメント