「子どもを守る」とは何か――。
親の言葉の裏にある事情と、がんばりすぎた母のSOS。
支援の形と心の距離が問われる、優しさを学ぶ第3話。
放送日時

2025年7月7日(月)
21:00スタート
フジテレビ
予告動画はこちらからご覧いただけます
「明日はもっと、いい日になる」 公式サイトはこちらからご覧いただけます
この記事にはドラマの内容に関するネタバレが含まれています。未視聴の方はご注意ください
ケース①:ネグレクトと「返せ」の叫び
前回の放送で、命の危機にあった子どもが、やっとの思いで児童相談所に保護される。
でもその後、母親が施設に怒鳴り込んで「返せ」と訴える――
しかも「誘拐だ」とまで言い出す。
驚くような展開だけれど、その背景には「手当がもらえなくなる」という現実的な事情もあった。
親が子どもを愛していないのか?
そうとは言い切れない。
でも、少なくとも「守る」という視点で物事を見ていないことは確かだった。
親の都合や生活のために、子どもの存在が“道具”のように扱われてしまうとき、
誰が子どもを守るのか?
このケースは、そんな問いを私たちに投げかけていたように思います。

子どもが一時保護所や児童養護施設に入所した場合、家庭に支給される手当や給付が減額されたり、支給停止になることがあります。
これは、親が直接子どもを養育していないと見なされるためです。
一時保護や施設入所で影響する可能性のある手当・給付
① 児童手当(通常の家庭に支給される手当)
- 施設で養育されている間は支給停止になるのが原則です
- ただし、施設が「受給者」として申請していれば、施設に支給されるケースもあります
② 児童扶養手当(ひとり親世帯などに支給)
- 子どもが長期間施設で生活する場合、「同一世帯とみなされない」として支給停止になることが多い
- 一時保護が一時的なものなら、影響が出ない場合もあります
③ 生活保護(母子加算など)
- 子どもが家にいない間は「人数減」として扱われるため、生活扶助額や母子加算が減額または打ち切りになる可能性がある
- 家計に大きな影響が出ることがあります
実際にあるケース
たとえば――
- 「施設に入れられたせいで手当がもらえなくなった」と親が不満を募らせる
- 経済的な不安が怒りや不満となって児相にぶつけられる
- 保護を“収入の妨げ”と捉え、「返して」と訴えるケースも
感想・考察として
お金の問題が、親の愛情や育児の姿勢をゆがめてしまうことはとても悲しいことです。
本来「守るため」の制度が、「困らせるもの」に見えてしまう瞬間――
そこには支援のあり方そのものの難しさが浮かび上がっています。

ケース②:「がんばりすぎた」お母さんのSOS
もうひとつのケースは、育児ノイローゼ。
肩こり、不眠、足が動かなくなるほどの心身の疲れ、そして「ごめんなさい」と繰り返す母親の姿。
完璧に育てようとするほど、自分を追い詰めてしまう。
その苦しさに、胸が締めつけられました。
子どもを置き去りにしてしまったという事実よりも、
「もう限界だった」と絞り出す母親の声に、心が揺れました。
そこには責めるよりも、支えることが必要だったと感じさせられます。

育児ノイローゼとは?
「育児ノイローゼ」とは、育児中のストレスや疲れ、不安が重なり、心や体が限界に近づいている状態のことです。
医学的には「産後うつ」「育児うつ」などに近いもので、気づかぬうちに心身が悲鳴を上げていることもあります。
身体的なサイン
- 肩こり・頭痛・吐き気・動悸
- 足が動かない、力が入らない
- 眠れない(不眠)/寝てもすぐ目が覚める
- 食欲がなくなる、または過食になる
心のサイン
- イライラしやすくなる
- 気分が沈んで涙が出てしまう
- 「自分はダメな母親だ」と責めてしまう(自己否定)
- 「ごめんなさい」が口癖になる
- 完璧にこなそうと無理してしまう(完璧主義)
危険なサイン(気づいてほしいこと)
- 子どもを置いて家を出たくなる
- 「子どもがいなければ…」とふと思ってしまう
- 子どもの泣き声を聞くとパニックになる
- 子どもにきつくあたってしまう自分が嫌になる
こうした状態は「疲れてるだけ」では済まされない心のSOSです。
特に「足が動かない」「涙が止まらない」などの症状は、限界のサインとも言えます。
なぜ起きるのか?
- 睡眠不足・孤独・相談できる人がいない
- 育児・家事・仕事を全部自分で背負ってしまう
- 「母親はこうあるべき」と思い込み、完璧を求める
- パートナーや周囲からの理解不足
救われるきっかけになる言葉
- 「あなたはよく頑張ってる」
- 「全部一人で抱えなくていい」
- 「手を抜くことは“悪”じゃない」
- 「“子どもを可愛く思えない日”があってもいい」
どうすればいいの?
- 信頼できる人に話す(友人・親・支援員など)
- 市区町村の「子育て相談窓口」「保健師」に連絡
- 一時保育やファミサポなどを活用して“ひとり時間”をつくる
- 心療内科や精神科に相談する(必要なら投薬もあり)
まとめとして
育児ノイローゼは「特別な誰かに起きること」ではなく、誰にでも起こりうる心の疲労です。
弱さではありません。
むしろ、限界まで頑張った証拠です。
「助けて」が言えなかった人に、そっと寄り添える社会であってほしい――
そんな思いを、ドラマや日常の中で忘れずにいたいと感じます。
支えるための仕組みも、確かにある
ドラマの中では、子どもを一時的に預けられる「ショートステイ」や、
ベビーシッター利用に対する補助の制度も紹介されていました。
「ひとりでがんばらなくていい」
そう言ってくれる制度や人がいることを、もっと多くの人が知っていてほしい。
そして、遠慮せずに頼っていいんだと思える世の中であってほしい――そう強く思いました。
「その子だけを見ていればいい」という言葉
焦る必要はない。
他の子と比べなくていい。
その子のペースで、ちゃんと育っていくから。
このメッセージは、育児に関わるすべての人にとって救いになる言葉でした。
親もこどもも「こうあるべき」に縛られすぎないでいい。
自分たちの歩幅で生きていくことの大切さを、そっと教えてくれるような第3話でした。


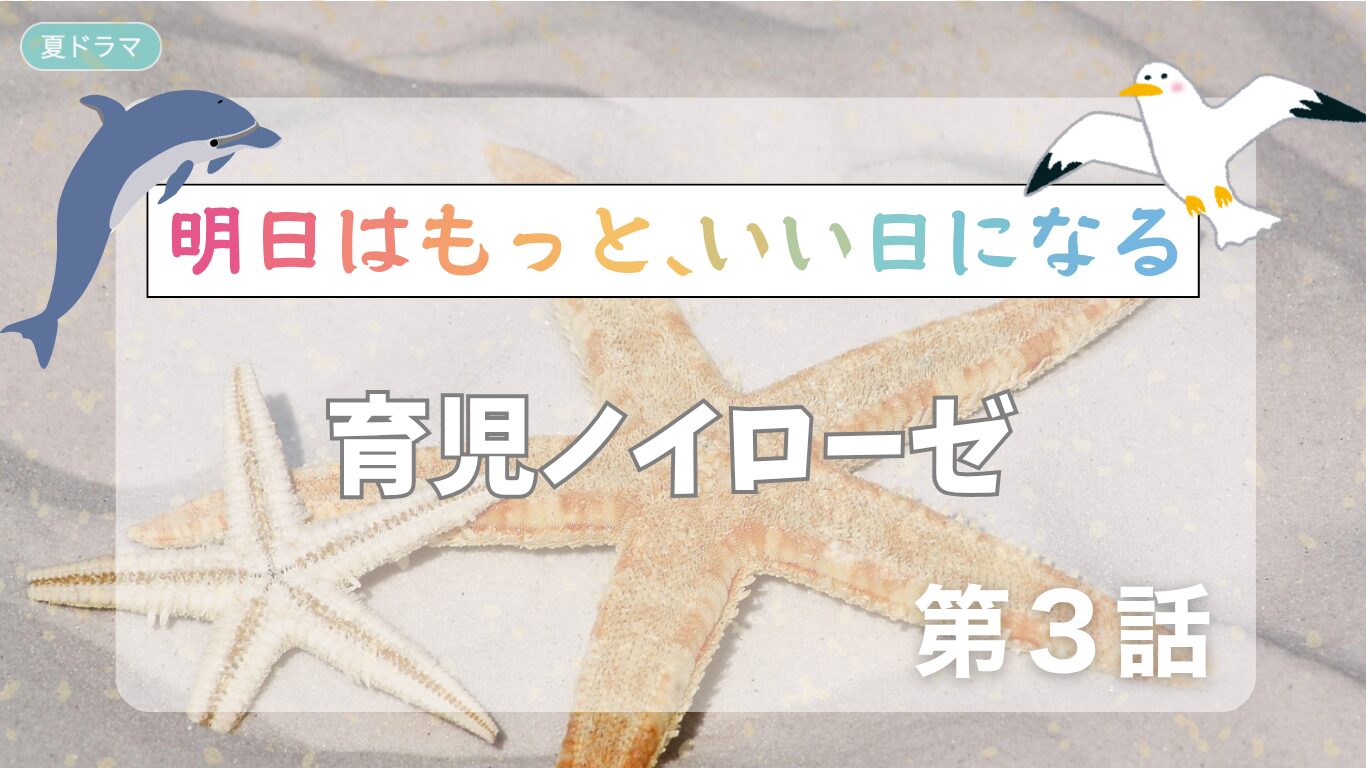
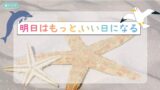


コメント