\競技かるたに青春をかける高校生たちの物語/
放送日時
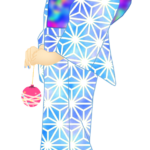
2025年7月9日(水)
22:00スタート
日本テレビ
予告動画はこちらからご覧いただけます
【ちはやふるーめぐりー】 公式サイトはこちらからご覧いただけます
この記事にはドラマの内容に関するネタバレが含まれています。未視聴の方はご注意ください
競技かるたを知るほどに、青春の奥行きが見えてきた
『ちはやふる-繋ぐ-』を観ていると、ただ札を取るだけじゃない、競技かるたの奥深さにどんどん引き込まれていきます。
最初は「百人一首を覚える競技なのかな」くらいに思っていたけれど、それだけじゃなかった。
そこには記憶・反応・心理戦・体力までもが絡み合った、まさに「静かなる格闘技」でした。
競技かるたの覚え方|基本から実践まで
① 百人一首の「下の句」を全部覚える
競技かるたでは、読み手が「上の句」を詠み、選手は「下の句(取り札)」を取ります。
なので、まずは下の句100首を覚えることが最重要!
覚え方のコツ:
- スマホアプリ(百人一首暗記アプリ)を活用
- 書いて覚える・読んで録音→聞く
- 1日10枚ずつなど、小分けにして繰り返す
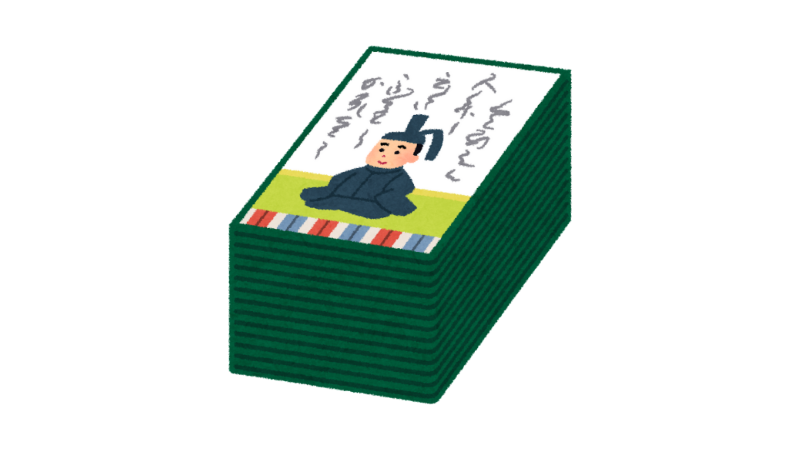
② 「決まり字」を覚える(暗記の近道!)
競技では、何文字で札が確定するかを覚えるのが実践的です。これを「決まり字」といいます。
| 決まり字 | 説明 |
|---|---|
| 1文字 | 「む」「す」「し」など、聞いた瞬間に確定 |
| 2〜3文字 | 「ちは」「ちぎ」など、少し長めで判断可能 |
| 多文字 | 「あさぼらけ〜」など、最後まで聞かないと確定しない札 |
早く札を取るには、決まり字を覚える=反射的に反応できるようにするのがポイントです!
③ 札の配置を覚える(並び順の記憶)
試合では自分の陣に25枚の札を置きますが、札の場所を覚えていないと勝てません!
おすすめは「3列×3段」の配置を使って、
- 「あの札は右端の真ん中」
- 「この札は左奥に置いた」
というように、札の場所ごとに“イメージ記憶”する練習をします。
指で札を触りながら位置を体で覚える人も多いです。
④ 読みのリズムに慣れる
試合では、プロの読み手による詩のテンポ・抑揚がカギになります。
- 音源やCD、YouTubeなどで「読み上げ音声」に慣れる
- 自分でも読みながら取ってみる
声に出して読んで、耳と口と手で覚えるのがとても効果的です!
競技かるたの世界では、「下の句」100首を全部覚えるのが大前提。
でもそれに加えて、“歌番号”で札を識別したり、耳で覚えたり、配置を体で記憶したりする。
もう、暗記っていうより“修行”に近いんじゃないかと思ってしまう(笑)。
「友札」は焦る!聞き分けの緊張感
なかでも驚いたのが「友札」という存在。
たとえば「しのぶ〜」で始まる札が4枚もあるなんて、知らなかった!
上の句だけじゃ札が確定しないから、決まり字を長く聞いてから動く。
でもそれって、一瞬の遅れが命取りになるんですよね…。
あのピリピリした空気、観てるだけで緊張してくる。

得意札って、“私だけの一枚”みたいで素敵
一方で、選手それぞれに「得意札」があるのも面白い。
この札なら誰にも負けない、っていうのがあるなんて、かっこいいし、ちょっと羨ましい。
自分の名前にちなんだ札とか、好きな和歌とか、心の支えになる札があるって素敵ですよね。
私にも、そんなふうに「これは譲れない!」って言える何か、あるのかなって考えさせられました。
大山札と囲い手——守る技術もまた、美しい
そして「大山札」。
似た札が多くて、間違いやすい札のことをそう呼ぶらしいんですが、
それに対する技が「囲い手」。
試合でお手つきを避けるために、札の周りを囲むようにして構える姿が、とても静かで美しくて、でも内側では烈火のような集中力を燃やしている。
そういうの、胸が熱くなります。
まとめ:覚えるだけじゃない、“生き方”を感じた
競技かるたって、たしかに札を覚える競技だけど、
もっと言えば、「どう向き合うか」「どう挑むか」という人生の姿勢がそのまま出る競技なんだと感じました。
覚え方にも工夫があって、札にも性格があって、それに挑む人の心も映る。
『ちはやふる』の世界がこんなにも深く、あたたかく、自分に問いかけてくるとは思わなかった。
少しずつでもいいから、私も百人一首、覚えてみようかな。





コメント