総合診療医は、“正解”を押しつけない医師。だからこそ、患者にとってかけがえのない存在だ。
\原作は富士屋カツヒトさんの医療漫画/
放送日時

2025年7月13日(日)
21:00スタート
TBSテレビ
予告動画はこちらからご覧いただけます
「19番目のカルテ」 公式サイトはこちらからご覧いただけます
この記事にはドラマの内容に関するネタバレが含まれています。未視聴の方はご注意ください
見どころ紹介
第3話で描かれたのは、声を職業とするアナウンサーが、がんと向き合う物語。
診断された病名は「粘表皮癌」。早期発見できたとはいえ、手術をすれば命は救えるが、声は元通りになるとは限らない。
粘表皮がんは、唾液をつくる「唾液腺」にできるがんの一種です。
耳の下やあごの下、舌の奥などにしこりとして現れることがあります。
がんの進行はゆっくりなことが多く、早期発見すれば命を守れる可能性も高いですが、
声・表情・飲み込みに関わる神経に影響することもあるため、
声を仕事にしている人にとっては大きな決断を迫られます。
大切に育ててきた声を守りたい。けれど、生きることもあきらめたくない。
どちらを選んでも、何かを失うかもしれない。
そんな選択の場に立たされたとき、患者の心の揺らぎにそっと寄り添ったのが、徳重先生でした。

「がんになった時、どう考えるべきか」という精神的な支えにもなる一冊です
総合診療科の真価が問われた回
このドラマを通して感じるのは、総合診療科の必要性が、ようやく語られはじめたということ。
どこの病院にもあってほしい。そう願わずにはいられません。
なぜなら、患者は常に迷っているから。
「この症状はどこに行けばいいのか?」
「治療の選択に後悔しないだろうか?」
「誰かにちゃんと話を聞いてほしい」
どの立場でも、患者の“納得”に重きを置く姿勢がぶれないのが特徴です。
健康に対する「正しい基本」が凝縮されている一冊です
総合診療医の3つの柱とは?
総合診療科の医師は「何でも診るお医者さん」と呼ばれることがありますが、実は3つの重要な役割を担っています。
総合診療医は、ただ病気を診るだけでなく、
「話を聞き、つなぎ、支える」という、患者にとって最も身近で頼れる医師。

1、ゲートキーパー(門番)
病気の入口に立ち、最初に患者の話を聞く役割。
- 病気の見逃しを防ぐ
- 不安な患者に“最初に話を聞いてくれる存在”
2、ファミリーメディスン(地域とつながる医師)
治療だけでなく、患者の“生活背景”まで見守る医師。
- 高齢者の慢性疾患や多病の管理
- 退院後の生活設計(訪問診療・地域連携)
- 家族関係や生活習慣にも配慮
3、コンダクター(医療の指揮者)
専門医との連携を調整し、患者の治療をスムーズにつなぐ存在。
- 複数の診療科にまたがる疾患の「まとめ役」
- 患者が“迷子”にならないように支える
- 治療のゴールを患者と一緒に考える
心に残った言葉と対話
「どの道を選んでも、あなたの人生はこの先も続いていく」
この一言に、どれほどの想いが詰まっているか。
医者の願いは「助けたい」。
患者の願いは「納得したうえで、精一杯生きたい」。
それが一致することは、案外難しい。
だけど、ぶつかりながらも対話を続ける中で、患者自身が「生きる覚悟」を決めていく。
それこそが、医療の本質ではないかと思わされました。

個人的な感想
声を失うかもしれないという不安。
それは、職業人としてだけでなく、「自分らしさ」を失う恐れでもあります。
それでも最終的に、患者自身が納得し、自分の人生を選ぶという流れが、胸にじんと響きました。
“うまくやるのは無理無理”。
患者の欲しいものと医者の望む結果のあいだに立ち、揺れながらも共に悩む――
それが、総合診療医の仕事なのだと、改めて感じました。
次回は
糖尿病の患者さん。
病気とともに生きるというテーマが、どのように描かれるのか、また静かに心に残る回になりそうです。

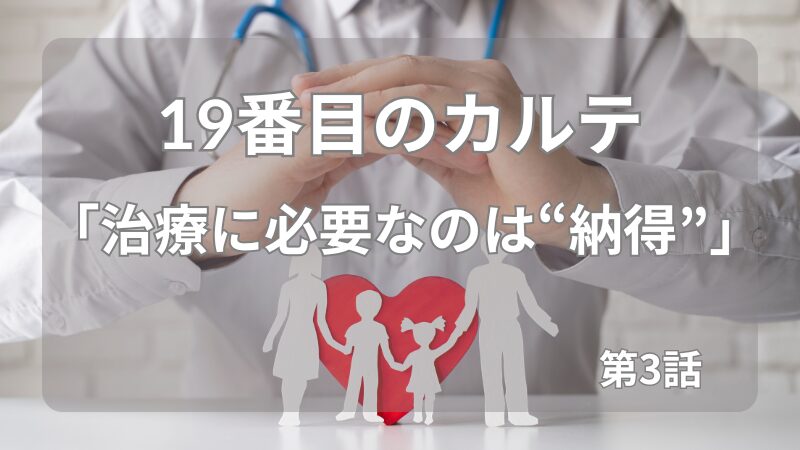


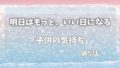
コメント